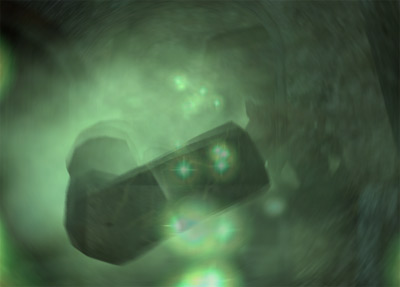ずっと
Ancient Tales of the Dwemer, Part VI: Chimarvamidium 編集者注
・・・Nordとの戦いにおいて、ChimerとDwemerは手を取り合って戦い、その後数百年間は平和な状態にあった、と色んな文献で学んだが、流石にすんなりとはいかなかったらしい。こうした諍いはたまに起きていたんだろうな。Nerevarさんもさぞ胃が痛かったことだろう。
戻る
進む